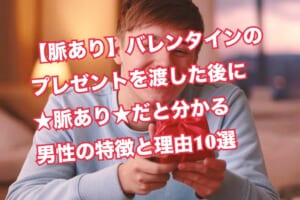ぐったりとしていたそうじゃ。
彼女は明らかに死んでいるように見え、実際に死んでいたのであろう。しかし男は半狂乱で彼女の名を呼び、目を覚ませと虚しく繰り返すばかりであった。
すっかり日が暮れて、あたりが真っ暗になった頃、男はようやく少しばかり正気に戻った。そして、しかるべき機関に事故対応と救助を願おうと携帯を手にしたが、そこは圏外であった。男は車を出ようとしたが、ドアがひしゃげてしまって出られない。このまま、救助も呼べず真っ暗闇の山で一夜を明かすなど恐ろしくてしかたない。
「誰か、助けてくれ。誰でもいいから……」
男はふだん、神も仏も信じなかったため、そのように「誰でもいいから」と心の底から願った。すると、どこかから声が聞こえてきた。
「・・・助けてやろうか」
男は驚き、車の外に目を凝らした。しかし、闇が広がるばかりで誰の姿も見えなかった。車の中にはとうぜん、死んだ彼女のほかに誰もいない。気のせいかと思ったそのとき、またはっきりと、
「・・・助けてやろう」
「何をしてほしい」
と、聞こえてきた。その声は男自身の頭の中に響いていた。これは幻聴かもしれない、と男は思ったが、藁にもすがる思いで、
「救助に来てほしい。なるべく早く、ここから出たい」と言った。すると、声は、
「いいだろう」
「それだけか。ほかにないのか」
「なんでも願ってみろ」
と応えた。男はそれなら、と、
「彼女を生き返らせくれ!」と懇願した。
すると、声は今度は、